えっ?この飛行機、こんなに小さいの!?
国内線に搭乗する際、ふと目にする“100席未満”という表記。「小型機ってどうなの?」「揺れやすいって本当?」そんな不安や疑問、ありますよね。
実は100席未満の小型機は、日本の地域路線や離島便などで重要な役割を果たしている存在。都市間移動とはひと味違った航空体験ができるのも魅力です。
この記事では、100席未満の国内線が就航している主な路線、採用されている機材の特徴、乗り心地や注意点まで、初めての方にもわかりやすく解説します。
「いつもと違う飛行機に乗るかも…」と少しでも不安な方、ぜひチェックしてみてください!
100席未満の国内線路線は主に地方・離島路線で活躍
路線規模や需要に合わせて、小型機が効率的に運航されている
国内の航空ネットワークでは、地域間の需要に応じて機材が使い分けられています。100席未満の機材は特に以下のようなケースで多く使用されます:
- 地方都市間を結ぶ短距離路線(例:名古屋〜但馬)
- 離島と本土を結ぶ路線(例:鹿児島〜屋久島)
- 滑走路が短い空港(例:奥尻空港、八丈島空港)
こうした地域では、大型ジェット機の運航が難しいため、小型プロペラ機や小型ジェットが活躍しています。
就航路線の例:JAC・HAC・FDAなどが中心
代表的な100席未満機を使用する国内路線は以下の通りです:
- JAC(日本エアコミューター):鹿児島〜種子島・喜界島など
- HAC(北海道エアシステム):札幌(丘珠)〜釧路・函館
- FDA(フジドリームエアラインズ):名古屋(小牧)〜出雲・高知
多くは地方空港から地方空港への“地域密着型”の路線となっています。
100席未満の機材はどんな飛行機?特徴や機内環境を解説
主な機材:ATR42/72・ボンバルディアDHC8・エンブラエルE170など
国内線で運用されている100席未満の主な機材は以下の通り:
- ATR42/72(ターボプロップ機)
- DHC-8-400(ボンバルディアQ400)
- エンブラエル170/175(小型ジェット機)
特にJACやHACはプロペラ機を多く採用し、FDAやANAの一部路線ではエンブラエル機が使われています。
座席構成・空調・サービスの違いに注意
100席未満の小型機では、以下のような違いがあります:
- 2-2配列や1-2配列の狭めの座席
- 手荷物収納スペースが小さく、キャリーケースが入らないことも
- 機内サービスが簡素(ドリンクなし or 限定)
大手機材と違い、静粛性や揺れに関してもやや敏感になることがあります。
100席未満の路線に乗る際の注意点と搭乗のコツ
揺れやすい傾向があるので、体調管理や酔い止めの準備を
プロペラ機や小型ジェット機は、大型機に比べて気流の影響を受けやすく、揺れを感じやすい傾向があります。乗り物酔いしやすい方は酔い止め薬を事前に服用しておくのがおすすめです。
空港の搭乗口が別棟やバス移動になることも
100席未満の便では、搭乗口が空港本館とは異なる「小型機専用ターミナル」や、駐機場までバスで移動するケースもあります。余裕を持って空港入りするのが安心です。
手荷物のサイズ・重量制限に注意
客室上部の収納が限られるため、LCCや大型機と同じ感覚でキャリーバッグを持ち込むと「貨物室預け」になることも。機材により「持ち込み可能なサイズ」は明確に違うので、予約時に機材確認を。
まとめ|100席未満の国内線は地域の空を支える重要な路線
100席未満の国内線は、「地方と地方」「離島と本土」をつなぐ、日本の交通インフラに欠かせない存在です。小型機ならではの特徴を知っておくことで、快適に、安心して利用できます。
次回の旅行や出張で「ちょっと小さい飛行機かも?」と感じたら、この記事を思い出していただければうれしいです。

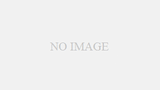
コメント